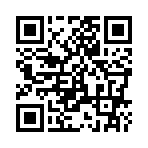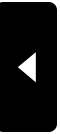2016年10月18日
ルアーメイキング1-6(セルロースで下地作り)
修理をしたスマホの話ですが、結局ラインはもとに戻せませんでした。
1日たって電話番号は認証されるようになりましたが、電話番号だけではもとには戻らず、メールアドレスも登録していなかったため仕方なく新規登録し直しました。
まあ、私のようなオヤジには、ラインする相手もあまりいないので、大したことなかったのですが、今度はメールアドレスもちゃんと登録しておきました。
さて、ルアーメイキングの話の続きです。
ブランクの成形が終わったら、セルロースセメントでブランクの下地コーティングをします。
今回使ったのはハードウッドで、中でも比較的硬いバスウッドですので、強度的には下地のコーティングはいらないのかもしれません。
ただ、木材は水を吸うと膨張して、表面の塗装が割れることがありますので、防水の意味でも下地コーティングは必要でしょう。
下地のコーティング剤としては、セルロースセメントや1液ウレタンクリアーが考えられますが、私はまず、セルロースセメントでコーティングします。
それも、薄め液で倍くらいに薄めたセルロースセメントを使います。
削り終わって最初のコーティングは、皮膜を作って表面を硬くすると言うよりも、木材にしみこませることを目的に行います。

ブランクを薄めたセルロースに1分位浸して十分にしみこませます。
セルロースからルアーを抜き上げたら、そのまま容器の上で液が垂れなくなるまでしずくを落とします。
乾燥台につるして丸1日乾燥させます。

なぜ、ウレタンを使わないのかというと、ウレタンクリアーは薄め液を入れても十分に希釈されないことと、ウレタンには硬化した後溶剤に犯されない性質があるからです。
前に序章のところでも書きましたが、セルロースセメントは乾いた後も溶剤で溶け出すため、トップコートとして使うとすぐに汚くなってしまいます。
しかし、下地コーティングとしては、先に塗ったセルロースを、後から塗ったセルロースが溶かしながら一体化して皮膜を形成するので、手間を掛けずにコーティングができます。
溶剤に犯されないウレタンを重ねてどぶ漬けするためには、一度乾いたあとの表面に足付けと呼ばれるキズを付けて、そこに上から塗る塗料を染みこませて一体化させる必要があります。
この方法でも塗料は一体化しているわけではありませんので、衝撃により剥離することがあります。
セルロースであれば、足付けをしなくても塗料が一体化してくれるので、剥離するようなことはありません。

薄めたセルロースにどぶ漬けして、乾いたら240番のサンドペーパーで表面をなめらかにして、再度セルロースにどぶ漬けします。
ハードウッドでルアーを作る場合で、3回程度この作業を繰り返します。
3回コーティングが終わったら、ある程度の防水性が期待できますので、この時点でリグやパーツを組んでスイムテストを行います。
また後でも触れたいと思いますが、スイムテストの後は1液ウレタンで下地コーティングを行います。
セルロースセメントで最後まで下地処理を行えれば良いのですが、それは推奨されません。
それは、セルロースの皮膜の上にウレタンを塗ると、「中ウミ」状態になる恐れがあるからです。
私は経験したことがありませんが、「中ウミ」状態とは、セルロースの皮膜を強い溶剤のウレタンが溶かし、セルロースが乾かないうちにウレタンが表面で固まり、フタをしてしまうため、セルロースがいつまでも乾かないでいる状態のことを言います。
こうならないためにも、セルロースで薄く防水のための皮膜を作ったら、1液ウレタンでコーティングして厚い皮膜を作り、その上で塗装を行います。
つづく
1日たって電話番号は認証されるようになりましたが、電話番号だけではもとには戻らず、メールアドレスも登録していなかったため仕方なく新規登録し直しました。
まあ、私のようなオヤジには、ラインする相手もあまりいないので、大したことなかったのですが、今度はメールアドレスもちゃんと登録しておきました。
さて、ルアーメイキングの話の続きです。
ブランクの成形が終わったら、セルロースセメントでブランクの下地コーティングをします。
今回使ったのはハードウッドで、中でも比較的硬いバスウッドですので、強度的には下地のコーティングはいらないのかもしれません。
ただ、木材は水を吸うと膨張して、表面の塗装が割れることがありますので、防水の意味でも下地コーティングは必要でしょう。
下地のコーティング剤としては、セルロースセメントや1液ウレタンクリアーが考えられますが、私はまず、セルロースセメントでコーティングします。
それも、薄め液で倍くらいに薄めたセルロースセメントを使います。
削り終わって最初のコーティングは、皮膜を作って表面を硬くすると言うよりも、木材にしみこませることを目的に行います。

ブランクを薄めたセルロースに1分位浸して十分にしみこませます。
セルロースからルアーを抜き上げたら、そのまま容器の上で液が垂れなくなるまでしずくを落とします。
乾燥台につるして丸1日乾燥させます。

なぜ、ウレタンを使わないのかというと、ウレタンクリアーは薄め液を入れても十分に希釈されないことと、ウレタンには硬化した後溶剤に犯されない性質があるからです。
前に序章のところでも書きましたが、セルロースセメントは乾いた後も溶剤で溶け出すため、トップコートとして使うとすぐに汚くなってしまいます。
しかし、下地コーティングとしては、先に塗ったセルロースを、後から塗ったセルロースが溶かしながら一体化して皮膜を形成するので、手間を掛けずにコーティングができます。
溶剤に犯されないウレタンを重ねてどぶ漬けするためには、一度乾いたあとの表面に足付けと呼ばれるキズを付けて、そこに上から塗る塗料を染みこませて一体化させる必要があります。
この方法でも塗料は一体化しているわけではありませんので、衝撃により剥離することがあります。
セルロースであれば、足付けをしなくても塗料が一体化してくれるので、剥離するようなことはありません。

薄めたセルロースにどぶ漬けして、乾いたら240番のサンドペーパーで表面をなめらかにして、再度セルロースにどぶ漬けします。
ハードウッドでルアーを作る場合で、3回程度この作業を繰り返します。
3回コーティングが終わったら、ある程度の防水性が期待できますので、この時点でリグやパーツを組んでスイムテストを行います。
また後でも触れたいと思いますが、スイムテストの後は1液ウレタンで下地コーティングを行います。
セルロースセメントで最後まで下地処理を行えれば良いのですが、それは推奨されません。
それは、セルロースの皮膜の上にウレタンを塗ると、「中ウミ」状態になる恐れがあるからです。
私は経験したことがありませんが、「中ウミ」状態とは、セルロースの皮膜を強い溶剤のウレタンが溶かし、セルロースが乾かないうちにウレタンが表面で固まり、フタをしてしまうため、セルロースがいつまでも乾かないでいる状態のことを言います。
こうならないためにも、セルロースで薄く防水のための皮膜を作ったら、1液ウレタンでコーティングして厚い皮膜を作り、その上で塗装を行います。
つづく