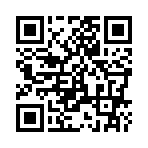2016年03月11日
ロッドメイキング1-21
今年もこの日がきました。
私は偉そうなことは何も言えないけど、全ての被災された方にお見舞い申し上げます。
日本人が忘れてはならない日 3.11

さて、話は変わってロツドメイキングの話。
2回目の塗料の混合です。1回目と同じように主液10グラム位を目安に、紙コップに入れます。
購入した主液の量が40mlなので、2回使うともう半分無くなります。
主液の4分の1の重さの硬化剤を計って入れます。
ここで、混ぜ合わせる前に、ウレタンシンナーを入れます。
ある程度ゆるくなるように希釈して、混ぜ合わせます。気泡がかまないようにゆっくり混ぜ合わせます。
しかし、シンナーの量が少なかったのか、少し気泡がかんできました。
また、少し希釈して混ぜ合わせます。
気泡がある程度残っていますが、このまま置いて置きます。
シンナーでゆるく希釈しているので、今度はある程度の粘度が出てくるまでしばらく置いておきます。
2時間位放置して粘度を見てみると、だいぶ上がってきたように思います。
はっきり言って、気温が低すぎるので、ウレタンの粘度が高いのかもしれません。
夏場にやれば、もっとサラサラになっているのかもしれませんが、冷えて粘度が上がったのか、シンナーが揮発して粘度があがったのかがわかりません。
とりあえず、混ぜ合わせた棒の先から垂らしてみると、ソフトクリーム状に山になるようになってきました。
(この塗り頃になった粘度の見分け方の表現はどこで見たんだったけ?)
そろそろ、塗り頃のようなので、塗装してみることにします。
ブランクを塩ビパイプで延長して、ボイジャーバッテリーにガムテープで固定。
バッテリーの上下を新聞紙で養生して、ポリ容器に塗料を入れます。
この辺は試し塗りで失敗したときと同じ手順です。
あまり厚く着きすぎるのもいやですが、ツヤが出ないのもいやなので、塗装するスピードを考えます。
ティップが厚塗りになるのが一番いやなので、ティップの部分はある程度ゆっくり抜こう。
バットはデカールの部分がまだ少しでこぼこがあるので、少し厚めに塗ろう。
ということで、始め早く、ティップに向けてスピードを緩めるイメージです。
それでは、塗ってみます。せーの
おっ!行ったか?
ゴムシートの穴も元に戻っていて、液だれも無し。塗料もこぼさずに塗装できました。
仕上がりは…

書き忘れていましたが、私はロッドやルアーのハンドメイドを秘密の小部屋という自分の部屋で行っています。
これは、家を新築するときにどうしてもほしくて作った、車庫からつづくコンクリート敷きの部屋です。
この小部屋を作りたくて家を建てたと言ってもいいくらいです。(家族に怒られそうですが…)
当初は、この小部屋を使って、ルアーやロッドの塗装、スノーボードのワックス掛けなどを全て行うつもりでしたが、思った以上に部屋に荷物が入り過ぎて、思うような作業スペースが取れませんでした。
そこで、ロッドの塗装など大きいものの塗装や、スノーボードのワックス掛けを車庫の中で行うようになったのです。
車庫の中には40ワットの蛍光灯が2本の照明と、後で自分で取り付けた、20ワットの蛍光灯が1本あるのですが、明るさの点で言えば充分とは言えません。
前置きが長くなりましたが、ポリ容器をうまく抜いて塗装ができたと思っても、仕上がりまでは良く確認ができなかったのです。
バッテリーからブランクを外して、逆さにつるして乾燥させます。
1~2時間で乾燥するとのことです。
この次点ではツヤツヤの仕上がりとなったかどうかは判断できません。
乾燥を待って、明るいところで確認してみます。
つづく
私は偉そうなことは何も言えないけど、全ての被災された方にお見舞い申し上げます。
日本人が忘れてはならない日 3.11

さて、話は変わってロツドメイキングの話。
2回目の塗料の混合です。1回目と同じように主液10グラム位を目安に、紙コップに入れます。
購入した主液の量が40mlなので、2回使うともう半分無くなります。
主液の4分の1の重さの硬化剤を計って入れます。
ここで、混ぜ合わせる前に、ウレタンシンナーを入れます。
ある程度ゆるくなるように希釈して、混ぜ合わせます。気泡がかまないようにゆっくり混ぜ合わせます。
しかし、シンナーの量が少なかったのか、少し気泡がかんできました。
また、少し希釈して混ぜ合わせます。
気泡がある程度残っていますが、このまま置いて置きます。
シンナーでゆるく希釈しているので、今度はある程度の粘度が出てくるまでしばらく置いておきます。
2時間位放置して粘度を見てみると、だいぶ上がってきたように思います。
はっきり言って、気温が低すぎるので、ウレタンの粘度が高いのかもしれません。
夏場にやれば、もっとサラサラになっているのかもしれませんが、冷えて粘度が上がったのか、シンナーが揮発して粘度があがったのかがわかりません。
とりあえず、混ぜ合わせた棒の先から垂らしてみると、ソフトクリーム状に山になるようになってきました。
(この塗り頃になった粘度の見分け方の表現はどこで見たんだったけ?)
そろそろ、塗り頃のようなので、塗装してみることにします。
ブランクを塩ビパイプで延長して、ボイジャーバッテリーにガムテープで固定。
バッテリーの上下を新聞紙で養生して、ポリ容器に塗料を入れます。
この辺は試し塗りで失敗したときと同じ手順です。
あまり厚く着きすぎるのもいやですが、ツヤが出ないのもいやなので、塗装するスピードを考えます。
ティップが厚塗りになるのが一番いやなので、ティップの部分はある程度ゆっくり抜こう。
バットはデカールの部分がまだ少しでこぼこがあるので、少し厚めに塗ろう。
ということで、始め早く、ティップに向けてスピードを緩めるイメージです。
それでは、塗ってみます。せーの
おっ!行ったか?
ゴムシートの穴も元に戻っていて、液だれも無し。塗料もこぼさずに塗装できました。
仕上がりは…

書き忘れていましたが、私はロッドやルアーのハンドメイドを秘密の小部屋という自分の部屋で行っています。
これは、家を新築するときにどうしてもほしくて作った、車庫からつづくコンクリート敷きの部屋です。
この小部屋を作りたくて家を建てたと言ってもいいくらいです。(家族に怒られそうですが…)
当初は、この小部屋を使って、ルアーやロッドの塗装、スノーボードのワックス掛けなどを全て行うつもりでしたが、思った以上に部屋に荷物が入り過ぎて、思うような作業スペースが取れませんでした。
そこで、ロッドの塗装など大きいものの塗装や、スノーボードのワックス掛けを車庫の中で行うようになったのです。
車庫の中には40ワットの蛍光灯が2本の照明と、後で自分で取り付けた、20ワットの蛍光灯が1本あるのですが、明るさの点で言えば充分とは言えません。
前置きが長くなりましたが、ポリ容器をうまく抜いて塗装ができたと思っても、仕上がりまでは良く確認ができなかったのです。
バッテリーからブランクを外して、逆さにつるして乾燥させます。
1~2時間で乾燥するとのことです。
この次点ではツヤツヤの仕上がりとなったかどうかは判断できません。
乾燥を待って、明るいところで確認してみます。
つづく