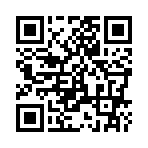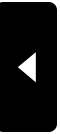2016年03月18日
ロッドメイキング1-26
昨日直したロッドにリールを付けて、準備完了!
明日は朝だけパリオカでも行こうか…

さて、ロッドメイキングの続き、
トップガイドの接着、ガイドの足削りが終わったら、ガイドをスレッドで固定します。
その際に使用するのがこれ、ちゃかちゃちゃっちゃちゃーん

ハンド・ロッド・ラッパ~~~
はい、ドラえもんの秘密道具のように登場したこの道具は、スレッドを巻くためのものです。
画像のものは私が自作したもので、材料費は3,000円位だったと思いますが、材料を探して何度もホームセンターと手芸店に通いました。
これを作った当時は、ハンドロッドラッパーが高くて、15,000円位しました。
1本目のロッドはこれなしで巻いてみましたが、手に力が入りすぎて指をつりそうになりながら巻いたので、絶対にロッドラッパーは必要だと感じました。
しかし、この先何本ロッドを自作するかわからない中で、15,000円の投資は考えられなかったので、自作することを選んだのです。
今は、富士工業製のものが6,000円位で売っていますので、そちらを買われた方が絶対にいいと思います。
ジャストエースを始めとするロッドメイキングの動画では、ロッドラッパーを使わずに手だけでスレッドを巻いていますが、単色で巻くなら素人でもできるかも知れませんが、ピンラインを入れたりするのは熟練の技がいります。

富士工業カタログより
左手で一重に巻いたスレッドの交点を押さえて1周巻きます。この間、右手はテンションを掛けながらスレッドを送り続けます。左手は交点を押さえてスレッドがずれないようにしながら、ブランクを回してスレッドを巻いていきます。
左手で押さえていた交点を過ぎるところまで巻いたら、左手を離してもスレッドはほぐれなくなります。
ただ、右手はテンションをかけ続けないと、巻いたスレッドはほぐれてきます。
左手はスレッドを押さえていなくても、ブランクは回し続けなければいけず、手を離すことはできません。
つまり、巻き初めてしまうと、巻き終わりまでは片手は必ず、スレッドを押さえ続けなければなりません。
これに、ピンラインを入れるとなると、最初に巻いたスレッドを左手で押さえながら、次の色のスレッドを最初に巻いたスレッドにかぶせて、その交点をさらに左手で押さえて1周巻かなければならず、ここで必ず失敗してスレッドがほぐれてしまいます。
文章で説明するのは、少し難しいです。
最初に巻いたスレッドもほぐれてやり直しとなると、思わずカッとなって、プチンと切れると物に当たりたくなります。
間違ってもブランクをへし折ったりしないでください。
例えは正しいかわかりませんが、初めてギターのコードを押さえるような感じで、素人がFを押さえているように手がつりそうになります。
その点、ハンドロッドラッパーを使えば、最初に交点を押さえて1周するところまでは手が離せませんが、そこまできてスレッドが止まってしまえば後は両手を離すことができます。
ピンラインのためのスレッドの入替えも、両手で行えるのですごく楽にできます。
巻き終わりに抜き糸を入れる時も、両手で行えるので失敗は少ないでしょう。
詳しいスレッドの巻き方は、富士工業のカタログを見るか、ジャストエースの動画を見るかしてください。
マタギの「完全なるルアーロッドの作り方」もDVDで売っているので、そちらを参考にするのも良いでしょう。
スレッドの選定についてですが、私は今はスケルターワークスのAスレッドを購入しています。
Aは細いスレッドの方です。

スレッドには色止めタイプと色が透けるタイプの2種類があります。
(画像右が色止めタイプ、左が透けるタイプ)
前は、マタギさんでスレッドを購入していたで、グデブロのスレッドでしたが、今はグデブロの物がなくなったので、一番簡単に手に入るスケルターワークスを購入しています。
(画像奥にあるのがグデブロ)
グデブロの色止めタイプは、NCP(ノンカラープリザーバー)と言われるもので、色止め用のカラープリザーバーという薬品がいらない物という意味です。
好みとしては、色が透けるタイプのスレッドに、カラープリザーバーを塗って透けるのを止め、エポキシコーティングをするのが一番仕上がりが良いと思っています。
色が透けるタイプのスレッドは、コーティングすると、とろっと飴を溶かしたようなツヤがでるので、そこが気に入っています。
最初から色止めタイプのものでは、そのツヤが出ないのです。
全体を色が透けるタイプで巻き、ピンラインを色止めタイプで巻くとか、全体を色止めタイプで巻き、わざとエポキシを薄く仕上げて、オールド感を出したりと、タイプ別に使い分ける方法もあるでしょう。
詳しい巻き方は先程も書いたとおり、富士工業のカタログなどを見てもらうとして、次回は、私なりに考えた、簡単な二重のピンラインの入れ方を説明します。
つづく
明日は朝だけパリオカでも行こうか…

さて、ロッドメイキングの続き、
トップガイドの接着、ガイドの足削りが終わったら、ガイドをスレッドで固定します。
その際に使用するのがこれ、ちゃかちゃちゃっちゃちゃーん

ハンド・ロッド・ラッパ~~~
はい、ドラえもんの秘密道具のように登場したこの道具は、スレッドを巻くためのものです。
画像のものは私が自作したもので、材料費は3,000円位だったと思いますが、材料を探して何度もホームセンターと手芸店に通いました。
これを作った当時は、ハンドロッドラッパーが高くて、15,000円位しました。
1本目のロッドはこれなしで巻いてみましたが、手に力が入りすぎて指をつりそうになりながら巻いたので、絶対にロッドラッパーは必要だと感じました。
しかし、この先何本ロッドを自作するかわからない中で、15,000円の投資は考えられなかったので、自作することを選んだのです。
今は、富士工業製のものが6,000円位で売っていますので、そちらを買われた方が絶対にいいと思います。
ジャストエースを始めとするロッドメイキングの動画では、ロッドラッパーを使わずに手だけでスレッドを巻いていますが、単色で巻くなら素人でもできるかも知れませんが、ピンラインを入れたりするのは熟練の技がいります。

富士工業カタログより
左手で一重に巻いたスレッドの交点を押さえて1周巻きます。この間、右手はテンションを掛けながらスレッドを送り続けます。左手は交点を押さえてスレッドがずれないようにしながら、ブランクを回してスレッドを巻いていきます。
左手で押さえていた交点を過ぎるところまで巻いたら、左手を離してもスレッドはほぐれなくなります。
ただ、右手はテンションをかけ続けないと、巻いたスレッドはほぐれてきます。
左手はスレッドを押さえていなくても、ブランクは回し続けなければいけず、手を離すことはできません。
つまり、巻き初めてしまうと、巻き終わりまでは片手は必ず、スレッドを押さえ続けなければなりません。
これに、ピンラインを入れるとなると、最初に巻いたスレッドを左手で押さえながら、次の色のスレッドを最初に巻いたスレッドにかぶせて、その交点をさらに左手で押さえて1周巻かなければならず、ここで必ず失敗してスレッドがほぐれてしまいます。
文章で説明するのは、少し難しいです。
最初に巻いたスレッドもほぐれてやり直しとなると、思わずカッとなって、プチンと切れると物に当たりたくなります。
間違ってもブランクをへし折ったりしないでください。
例えは正しいかわかりませんが、初めてギターのコードを押さえるような感じで、素人がFを押さえているように手がつりそうになります。
その点、ハンドロッドラッパーを使えば、最初に交点を押さえて1周するところまでは手が離せませんが、そこまできてスレッドが止まってしまえば後は両手を離すことができます。
ピンラインのためのスレッドの入替えも、両手で行えるのですごく楽にできます。
巻き終わりに抜き糸を入れる時も、両手で行えるので失敗は少ないでしょう。
詳しいスレッドの巻き方は、富士工業のカタログを見るか、ジャストエースの動画を見るかしてください。
マタギの「完全なるルアーロッドの作り方」もDVDで売っているので、そちらを参考にするのも良いでしょう。
スレッドの選定についてですが、私は今はスケルターワークスのAスレッドを購入しています。
Aは細いスレッドの方です。

スレッドには色止めタイプと色が透けるタイプの2種類があります。
(画像右が色止めタイプ、左が透けるタイプ)
前は、マタギさんでスレッドを購入していたで、グデブロのスレッドでしたが、今はグデブロの物がなくなったので、一番簡単に手に入るスケルターワークスを購入しています。
(画像奥にあるのがグデブロ)
グデブロの色止めタイプは、NCP(ノンカラープリザーバー)と言われるもので、色止め用のカラープリザーバーという薬品がいらない物という意味です。
好みとしては、色が透けるタイプのスレッドに、カラープリザーバーを塗って透けるのを止め、エポキシコーティングをするのが一番仕上がりが良いと思っています。
色が透けるタイプのスレッドは、コーティングすると、とろっと飴を溶かしたようなツヤがでるので、そこが気に入っています。
最初から色止めタイプのものでは、そのツヤが出ないのです。
全体を色が透けるタイプで巻き、ピンラインを色止めタイプで巻くとか、全体を色止めタイプで巻き、わざとエポキシを薄く仕上げて、オールド感を出したりと、タイプ別に使い分ける方法もあるでしょう。
詳しい巻き方は先程も書いたとおり、富士工業のカタログなどを見てもらうとして、次回は、私なりに考えた、簡単な二重のピンラインの入れ方を説明します。
つづく
2016年03月17日
フォアグリップ修復
昨日は、2時頃から近所の野池を見に行った。
道路の表示は気温17℃!
花粉が飛んでるようで、鼻がムズムズする。
池に着いてみると、入りたいポイントにまさかのヘラ師二人!
対岸にもバサーが見える。
みんな考えることは一緒だな。
雪融け間もない平日だから、貸切を期待してたのに、完全に裏切られた。
小1時間、竿を出したが、反応無し…
子供の予防注射があったので、3時過ぎに終了。
初釣りは、無反応のまま終わり。

ダイワVIP52MHT
今シーズンから使おうと、中古で購入していたものを、昨日の釣りのために準備していたら、
リールシートを締めていたらなんと…
フォアグリップ破損!
パックリコルクが割れてしまいました。
エポキシ接着剤の30分硬化のものを使い接着。

マスキングテープと、タコ糸で固定して丸一日乾燥させました。
接着剤を塗っている途中、コルクがボロボロ剥がれてきましたが、つまよう で元 に戻しながら接着。
何とか成功しているようです。

このロッドに付いていたフォアグリップも、コルクが割れて壊れていたので、ハートランドXのグリップから移植していたのですが、コルクが割れてしまいました。
この手のフォアグリップは、中古で売っているものも良く破損しているものを見かけるので、リールシートを締める時は注意が必要です。
道路の表示は気温17℃!
花粉が飛んでるようで、鼻がムズムズする。
池に着いてみると、入りたいポイントにまさかのヘラ師二人!
対岸にもバサーが見える。
みんな考えることは一緒だな。
雪融け間もない平日だから、貸切を期待してたのに、完全に裏切られた。
小1時間、竿を出したが、反応無し…
子供の予防注射があったので、3時過ぎに終了。
初釣りは、無反応のまま終わり。

ダイワVIP52MHT
今シーズンから使おうと、中古で購入していたものを、昨日の釣りのために準備していたら、
リールシートを締めていたらなんと…
フォアグリップ破損!
パックリコルクが割れてしまいました。
エポキシ接着剤の30分硬化のものを使い接着。

マスキングテープと、タコ糸で固定して丸一日乾燥させました。
接着剤を塗っている途中、コルクがボロボロ剥がれてきましたが、つまよう で元 に戻しながら接着。
何とか成功しているようです。

このロッドに付いていたフォアグリップも、コルクが割れて壊れていたので、ハートランドXのグリップから移植していたのですが、コルクが割れてしまいました。
この手のフォアグリップは、中古で売っているものも良く破損しているものを見かけるので、リールシートを締める時は注意が必要です。
2016年03月16日
ロッドメイキング1-25
先週の土曜日出勤の代休で、今日は午後から休める予定。
天気が良ければフィールドでも見に行ってみようかな。
さて、ロッドメイキングの続きです。
トップガイドを接着したら、トップガイドにスレッドを巻いて、順に2番ガイド、3番ガイドと、スレッドで固定していきますが、スレッドを巻く前に、ガイドフットを削る必要があります。
ガイドの足削りと呼ばれる作業ですが、ロッドとガイドとの段差を少なくし、スレッドが乗りやすくなる効果があります。

画像は元のブランクTD-Sから外したガイド
「ガイドをしっかり固定し、足先の斜面に沿って、グッ、グッとヤスリを向こうに押すように削ります。」と、富士工業のカタログでは紹介されています。

富士工業カタログより
ヤスリを往復させないで、1方向にのみ削っていくとバリが出ないできれいに削れます。
これもどこかで紹介されていたと思います。
たしか、ジャストエースの動画だったと思いますが、最近、ユーチューブで探してみましたが、見つかりませんでした。
また、マタギさんの「完全なるルアーロッドの作り方」のビデオではハンディーベルトサンダーで削っていたように記憶していますが、なにせビデオデッキが壊れてから見ていないのであいまいです。
道具は、小型の金属製のヤスリであれば何でも良いと思います。
100均で売っているもので足りると思います。

「ブランクやスレッドをキズつけないよう、刃物のように鋭く削らないでください。」と、富士工業のカタログでは、注意してあります。
じゃあ、いったいどれ位削ればいいのかというと、はっきり言って最近の小さいガイドは
削る必要が無いのではと思っています。
私は、Nガイドが手に入らない時などや、少しティップを軽くしたい時などは、LNガイドのリングサイズ7を2、3番ガイドに使います。
LNSG7を買ってもらえばわかりますが、刃物のように鋭く削らないで、足削りをするのは困難です。
もうすでに、指に刺すと痛いくらい尖っています。
つまり、気持ち先を尖らす程度削ってやれば充分で、ほとんど削らなくても支障が無いと
思われます。
ただし、Nガイドなどの太いタイプのガイドや、大きいサイズのガイドは、ガイドフットの先が厚くなっていますので、先に向かって傾斜をつけるように削って、段差を無くしてあげる必要があります。
これは、ガイドを固定するスレッドの太さによっても変わってきます。
太いスレッドであれば、それほど気を遣わなくても良いが、細いスレッドを使うと、段差をスレッドが乗り越えられず、ガイドフットの下に潜り込んで行くため、段差は極力少なくしておきましょう。
トップガイドを接着すると、乾くまで次の作業に移れないので、その隙にガイドの足削りを行うと良いでしょう。
つづく
天気が良ければフィールドでも見に行ってみようかな。
さて、ロッドメイキングの続きです。
トップガイドを接着したら、トップガイドにスレッドを巻いて、順に2番ガイド、3番ガイドと、スレッドで固定していきますが、スレッドを巻く前に、ガイドフットを削る必要があります。
ガイドの足削りと呼ばれる作業ですが、ロッドとガイドとの段差を少なくし、スレッドが乗りやすくなる効果があります。

画像は元のブランクTD-Sから外したガイド
「ガイドをしっかり固定し、足先の斜面に沿って、グッ、グッとヤスリを向こうに押すように削ります。」と、富士工業のカタログでは紹介されています。

富士工業カタログより
ヤスリを往復させないで、1方向にのみ削っていくとバリが出ないできれいに削れます。
これもどこかで紹介されていたと思います。
たしか、ジャストエースの動画だったと思いますが、最近、ユーチューブで探してみましたが、見つかりませんでした。
また、マタギさんの「完全なるルアーロッドの作り方」のビデオではハンディーベルトサンダーで削っていたように記憶していますが、なにせビデオデッキが壊れてから見ていないのであいまいです。
道具は、小型の金属製のヤスリであれば何でも良いと思います。
100均で売っているもので足りると思います。

「ブランクやスレッドをキズつけないよう、刃物のように鋭く削らないでください。」と、富士工業のカタログでは、注意してあります。
じゃあ、いったいどれ位削ればいいのかというと、はっきり言って最近の小さいガイドは
削る必要が無いのではと思っています。
私は、Nガイドが手に入らない時などや、少しティップを軽くしたい時などは、LNガイドのリングサイズ7を2、3番ガイドに使います。
LNSG7を買ってもらえばわかりますが、刃物のように鋭く削らないで、足削りをするのは困難です。
もうすでに、指に刺すと痛いくらい尖っています。
つまり、気持ち先を尖らす程度削ってやれば充分で、ほとんど削らなくても支障が無いと
思われます。
ただし、Nガイドなどの太いタイプのガイドや、大きいサイズのガイドは、ガイドフットの先が厚くなっていますので、先に向かって傾斜をつけるように削って、段差を無くしてあげる必要があります。
これは、ガイドを固定するスレッドの太さによっても変わってきます。
太いスレッドであれば、それほど気を遣わなくても良いが、細いスレッドを使うと、段差をスレッドが乗り越えられず、ガイドフットの下に潜り込んで行くため、段差は極力少なくしておきましょう。
トップガイドを接着すると、乾くまで次の作業に移れないので、その隙にガイドの足削りを行うと良いでしょう。
つづく
2016年03月15日
ロッドメイキング1-24
最近、コンスタントにブログを見ていただいてるようで、閲覧数が上がっています。
まだ1日50件程度ですが、ありがたいことです。
早く魚の画像をアップしたいと思う今日この頃です。
さて、ロッドメイキングの続きですが、
ガイドを選んだら、ロッドにスレッドで固定していきます。
まず、トップガイドの取り付けですが、これだけは接着剤で固定します。
私が使うのはこれ!

2液混合のエポキシ接着剤です。
画像の左にあるものです。
トップガイドの接着には、画像右の富士工業ホットグルーを使うように紹介しているところもありますが、あくまでも応急用として売っているものなので私は使いません。
ロッドは高温の車内に置かれることもあるので、熱で溶けるものは、外れたり、ずれたりする恐れがあります。
そこで、エポキシ接着剤を選択するのですが、リメイクのことを考えると、あまり強いもので接着すると、トップガイドが取れなくなるので、5分硬化タイプが適当だと思います。
メーカーや商品に特にこだわりはなく、5分硬化なら何でも良いと思います。
トップガイドの取り付け位置は、最初にブランクからガイドを外す時にマーキングしておきます。
マーキングはブランクの一番根元の部分にしか出来ないので、トップガイドの向きと合わせるときは慎重にしてください。
エポキシ接着剤を同量で混合したら、1分くらいかけて良く混ぜ合わせます。
トップガイドの筒の中につまようじなどで、接着剤を入れ、ティップに差し込みます。
この時、マーキングとずれないように、慎重に位置を調整します。
はみ出た接着剤はそのまま乾燥させても、後でポロッと取り除けます。
拭き取る場合は、ガイドの向きがずれないように、アルコールランプの燃料で、きれいに拭き取ります。
接着の位置が決まったら、そのまま動かさ無いように、1日くらい乾燥させます。
つづく
まだ1日50件程度ですが、ありがたいことです。
早く魚の画像をアップしたいと思う今日この頃です。
さて、ロッドメイキングの続きですが、
ガイドを選んだら、ロッドにスレッドで固定していきます。
まず、トップガイドの取り付けですが、これだけは接着剤で固定します。
私が使うのはこれ!

2液混合のエポキシ接着剤です。
画像の左にあるものです。
トップガイドの接着には、画像右の富士工業ホットグルーを使うように紹介しているところもありますが、あくまでも応急用として売っているものなので私は使いません。
ロッドは高温の車内に置かれることもあるので、熱で溶けるものは、外れたり、ずれたりする恐れがあります。
そこで、エポキシ接着剤を選択するのですが、リメイクのことを考えると、あまり強いもので接着すると、トップガイドが取れなくなるので、5分硬化タイプが適当だと思います。
メーカーや商品に特にこだわりはなく、5分硬化なら何でも良いと思います。
トップガイドの取り付け位置は、最初にブランクからガイドを外す時にマーキングしておきます。
マーキングはブランクの一番根元の部分にしか出来ないので、トップガイドの向きと合わせるときは慎重にしてください。
エポキシ接着剤を同量で混合したら、1分くらいかけて良く混ぜ合わせます。
トップガイドの筒の中につまようじなどで、接着剤を入れ、ティップに差し込みます。
この時、マーキングとずれないように、慎重に位置を調整します。
はみ出た接着剤はそのまま乾燥させても、後でポロッと取り除けます。
拭き取る場合は、ガイドの向きがずれないように、アルコールランプの燃料で、きれいに拭き取ります。
接着の位置が決まったら、そのまま動かさ無いように、1日くらい乾燥させます。
つづく
2016年03月14日
ロッドメイキング1-23
昨日の柔道大会では、6年生チームは3位入賞!
低学年も3位入賞でした。
我が子は1回戦で、寝技一本負け。
チー ムも1回戦敗退で、課題の残る結果でした。

左からGNGG、ELNSG、GLNSG
さて、ガイドの話をもう少し。
富士工業のガイドの品番は最初のアルファベットがフレームを、次が形を、次がリングをそれぞれ表しています。
GLNSGで言うと、ゴールドフレーム、LN形、Sicリングのガイドとなります。
最初のアルファベットが無いのはガンスモーク仕上げ、T-が付くのがチタンフレームとなります。
上の画像のものは全てカタログ落ちしているので、ELNSGの代わりのPLNSGを選ぶか、在庫のある店を探して自分好みのものを見つけるしかありません。
ダブルフットの現行品で、MN形、KW形がありますが、どちらもゴールドフレームの設定は無く、また、画像一番左で使われているゴールドサーメットリングは現在作られていません。
これは、見た目がゴールドで、値段も高かったゴールドサーメットガイドよりも、性能の面でSicガイドのほうが上であるため 、取って替わられたのでしょう。
この辺の話は、富士工業のカタログにも詳しく書かれていますので、参考にしてください。
ガイドをダブルフットのものにすると、シングルフットのものの時よりも、スローテーパーになった感じがします。
これは何も付けていない、ロッドだけ振った時にそう感じるもので、ガイドが重くなった分、ティップの反応が遅れてくるからでしょう。
ただ、ロッド自体の硬さが変わるわけでは無いので、負荷をかけた時の曲がりは変わらないと思われます。
つまり、キャスト時や、リトリーブ時の感じは変わらないが、ティップでアクションを付けた時に、反応の遅さで、トップウォータールアーはアクションさせやすくなる効果があるのかなと勝手に思ってます。
最近のロッドはこの反応の遅さを嫌うため、軽量のガイドを付けているのでしょう。
PEラインを使っていると、ガイドへの糸がらみも気になります。
そういった要素もいろいろと考えて、自分好みのガイドを選択すると良いでしょう。
自分好みのガイドが決まったら、いよいよガイドの取り付けです。
つづく
低学年も3位入賞でした。
我が子は1回戦で、寝技一本負け。
チー ムも1回戦敗退で、課題の残る結果でした。

左からGNGG、ELNSG、GLNSG
さて、ガイドの話をもう少し。
富士工業のガイドの品番は最初のアルファベットがフレームを、次が形を、次がリングをそれぞれ表しています。
GLNSGで言うと、ゴールドフレーム、LN形、Sicリングのガイドとなります。
最初のアルファベットが無いのはガンスモーク仕上げ、T-が付くのがチタンフレームとなります。
上の画像のものは全てカタログ落ちしているので、ELNSGの代わりのPLNSGを選ぶか、在庫のある店を探して自分好みのものを見つけるしかありません。
ダブルフットの現行品で、MN形、KW形がありますが、どちらもゴールドフレームの設定は無く、また、画像一番左で使われているゴールドサーメットリングは現在作られていません。
これは、見た目がゴールドで、値段も高かったゴールドサーメットガイドよりも、性能の面でSicガイドのほうが上であるため 、取って替わられたのでしょう。
この辺の話は、富士工業のカタログにも詳しく書かれていますので、参考にしてください。
ガイドをダブルフットのものにすると、シングルフットのものの時よりも、スローテーパーになった感じがします。
これは何も付けていない、ロッドだけ振った時にそう感じるもので、ガイドが重くなった分、ティップの反応が遅れてくるからでしょう。
ただ、ロッド自体の硬さが変わるわけでは無いので、負荷をかけた時の曲がりは変わらないと思われます。
つまり、キャスト時や、リトリーブ時の感じは変わらないが、ティップでアクションを付けた時に、反応の遅さで、トップウォータールアーはアクションさせやすくなる効果があるのかなと勝手に思ってます。
最近のロッドはこの反応の遅さを嫌うため、軽量のガイドを付けているのでしょう。
PEラインを使っていると、ガイドへの糸がらみも気になります。
そういった要素もいろいろと考えて、自分好みのガイドを選択すると良いでしょう。
自分好みのガイドが決まったら、いよいよガイドの取り付けです。
つづく
2016年03月13日
2016年03月12日
ロッドメイキング1-22
今日は久しぶりの土曜日出勤。
と言っても事務所に清掃業者が入るので、その立ち合いだけで、特に急ぐ仕事も無い。
昨日は、人事異動の内示があったが、異動の対象では無かった。
さて、しごき塗装の続きですが、塗り直し1回目の塗装を終えて、しばらく乾かしてから見てみると、大半は上手く塗れてツヤツヤになっています。
やった!と思いましたが、良く見るとティップの方に気泡が付いて固まった、小さなぷつぷつが残っていました。
ガマン出来る範囲かとも思いましたが、ここは完璧を目指し、もう一度しごき塗装することにします。
何度目の塗装だ?
スポンジヤスリでぷつぷつを取り、脱脂してから塗装します。
今度は気泡が出来ないように、最初からある程度緩めにシンナーで 希釈して、しばらく置いてから塗装しました。
最初から付いていた塗装のでこぼこを除けば、ほぼ完璧な仕上がりではないでしょうか。
長かったしごき塗装の試行錯誤も、もようやく完成です。
これで、次回からは失敗しないで出来るでしょう。

塗装が終わった後は、いよいよガイドを取り付けて行きます。
前にも書きましたが、元のブランクに付いていたガイドと違う位置に付ける場合は、仮止めをしてバランスを見ながら、ガイドの位置を決めていかなければなりません。
今回の場合は、最初からガイドが7個で、ブランクの長さも変えていないので、元にあった場所にそのままガイドを付けて行きます。
ガイドがあった位置は、あらかじめトップガイドからリングの中心間を測ってメモしてあります。
ガイドの取り付けについては、次回以降にまわすとして、今回はガイドの選定について少し話ます。
元々付いていたガイドをそのまま利用するなら良いのですが、そのガイドが気に入らないとか、フレームが曲がってるとかなると、別なガイドを選ぶ必要があります。

日本で売られているガイドは、ほぼ富士工業さんのガイドです。
日本のロッドの99 %以上が富士工業のガイドが付いています。
ほとんど独占状態ですが、これは悪い意味ではなく、富士工業のガイドを選んで間違いないということです。
一部、富士工業以外のガイドを付けているロツドや、ガイドのみを売っているところもあります。
私が知る限りで、マタギさん、ブライトリバーさん、ハネダクラフトさん、オールドスクールさんなどで、そのほとんどが、デッドストックのもののようです。
オールドタックルのおもむきを楽しみたいならば、それを選択するのも良いでしょう。
また、実際に、用途によっては富士工業をしのぐ性能のものがあるのかも知れませんが、私は使ったことが無いのでわかりません。
しかし、それらのものは需要が少ないためか、手間がかかるためか、値段は高くなります。
そういった意味で、富士工業を選べば、安くて、性能の良いものが、手に入ります。
予算が許せば、ブライトリバーさんオリジナルのガイドは一度使ってみたいと思っています。
で、富士工業のガイドの中から、どのガイドを選択するのかですが、これは個人 好みになるので、何とも言えません。
ただ、リングはSic(シリコンカーバイトだっけ?)のものを選んで下さい。
まあ、他のものは選びたくてもあまり売ってませんが。
私は、トップウォーターロッドを作るので、ダブルフットのガイドを選択します。
前にも書きましたが、最近のロッドはニューガイドコンセプト(もう、新しくないかもです)が主流で、軽量、小口径のガイドを数多く付けます。
私は、ダブルフットの比較的大口径(リングサイズ8以上)を、トップガイド含めて7個を基準として取り付けます。
トップガイドから8、8、8、8、10、10、12の7個です。
今回選んだガイドは、トップガイドが富士工業CPST、2番ガイドからがCNSGです。
両方ともに廃盤で、カタログ落ちしています。
私は以前、レトロム247さんのネット通販で見つけて、3セット買ったのですが、他は全部使い、これが最後のセットです。
レトロムさんのネット通販ページが改修されたのに伴い、商品ページが無くなったので、もう購入することが出来ません。
もしかするとまだ、在庫があるのかも知れませんが、次に使いたくなった時に探してみようと思います。
ガイドと一緒に「ハンドメイド楽しんで下さい。」と、店長さんから暖かいメッセージが入っていたのを思い出します。
このガイドを選んだ理由は、こちら


私が所有する、スピードスティック#1-26HOBBに付いているガイドが、このCNSGのハードリング版だったからです。
オールドな雰囲気を残しながら、リングはSicで性能アップ!
めっちゃ格好良くないですか?
現行品でもハードリング版のNガイドは売っていますが、スピードスティックに付いているものとは違うようです。
ハードリングでも性能は十分なのかも知れませんが、やっぱりリングはSicでしょう。
ちなみに、CNSGの品番に付いているCとはクロームメッキのことで、現在は環境に優しく無いので、作られなくなったようです。
現行品で、似たものを探すと、E又はPの品番が付いたものを選択するしかありません。
また、NガイドもSicリングの設定のものはなく、ライト仕様のLNか、ミディアム仕様MNの品番のものを選ぶしかありません。
最近は、(最近でも無い?)ダブルフットのガイドも、Kガイドという前側に傾斜した糸絡みの少ないガイドに変わって来ているので、そちらの選択も出来ます。
ただ、今回のように、オールドな雰囲気を残しつつ、Sicガイドで、しかも安価にとなると、デッドストックのものを探すしかないので ネットで、注意深く探すか、古くからある釣具屋さんの在庫を探すかしかないのです。
つづく
と言っても事務所に清掃業者が入るので、その立ち合いだけで、特に急ぐ仕事も無い。
昨日は、人事異動の内示があったが、異動の対象では無かった。
さて、しごき塗装の続きですが、塗り直し1回目の塗装を終えて、しばらく乾かしてから見てみると、大半は上手く塗れてツヤツヤになっています。
やった!と思いましたが、良く見るとティップの方に気泡が付いて固まった、小さなぷつぷつが残っていました。
ガマン出来る範囲かとも思いましたが、ここは完璧を目指し、もう一度しごき塗装することにします。
何度目の塗装だ?
スポンジヤスリでぷつぷつを取り、脱脂してから塗装します。
今度は気泡が出来ないように、最初からある程度緩めにシンナーで 希釈して、しばらく置いてから塗装しました。
最初から付いていた塗装のでこぼこを除けば、ほぼ完璧な仕上がりではないでしょうか。
長かったしごき塗装の試行錯誤も、もようやく完成です。
これで、次回からは失敗しないで出来るでしょう。

塗装が終わった後は、いよいよガイドを取り付けて行きます。
前にも書きましたが、元のブランクに付いていたガイドと違う位置に付ける場合は、仮止めをしてバランスを見ながら、ガイドの位置を決めていかなければなりません。
今回の場合は、最初からガイドが7個で、ブランクの長さも変えていないので、元にあった場所にそのままガイドを付けて行きます。
ガイドがあった位置は、あらかじめトップガイドからリングの中心間を測ってメモしてあります。
ガイドの取り付けについては、次回以降にまわすとして、今回はガイドの選定について少し話ます。
元々付いていたガイドをそのまま利用するなら良いのですが、そのガイドが気に入らないとか、フレームが曲がってるとかなると、別なガイドを選ぶ必要があります。

日本で売られているガイドは、ほぼ富士工業さんのガイドです。
日本のロッドの99 %以上が富士工業のガイドが付いています。
ほとんど独占状態ですが、これは悪い意味ではなく、富士工業のガイドを選んで間違いないということです。
一部、富士工業以外のガイドを付けているロツドや、ガイドのみを売っているところもあります。
私が知る限りで、マタギさん、ブライトリバーさん、ハネダクラフトさん、オールドスクールさんなどで、そのほとんどが、デッドストックのもののようです。
オールドタックルのおもむきを楽しみたいならば、それを選択するのも良いでしょう。
また、実際に、用途によっては富士工業をしのぐ性能のものがあるのかも知れませんが、私は使ったことが無いのでわかりません。
しかし、それらのものは需要が少ないためか、手間がかかるためか、値段は高くなります。
そういった意味で、富士工業を選べば、安くて、性能の良いものが、手に入ります。
予算が許せば、ブライトリバーさんオリジナルのガイドは一度使ってみたいと思っています。
で、富士工業のガイドの中から、どのガイドを選択するのかですが、これは個人 好みになるので、何とも言えません。
ただ、リングはSic(シリコンカーバイトだっけ?)のものを選んで下さい。
まあ、他のものは選びたくてもあまり売ってませんが。
私は、トップウォーターロッドを作るので、ダブルフットのガイドを選択します。
前にも書きましたが、最近のロッドはニューガイドコンセプト(もう、新しくないかもです)が主流で、軽量、小口径のガイドを数多く付けます。
私は、ダブルフットの比較的大口径(リングサイズ8以上)を、トップガイド含めて7個を基準として取り付けます。
トップガイドから8、8、8、8、10、10、12の7個です。
今回選んだガイドは、トップガイドが富士工業CPST、2番ガイドからがCNSGです。
両方ともに廃盤で、カタログ落ちしています。
私は以前、レトロム247さんのネット通販で見つけて、3セット買ったのですが、他は全部使い、これが最後のセットです。
レトロムさんのネット通販ページが改修されたのに伴い、商品ページが無くなったので、もう購入することが出来ません。
もしかするとまだ、在庫があるのかも知れませんが、次に使いたくなった時に探してみようと思います。
ガイドと一緒に「ハンドメイド楽しんで下さい。」と、店長さんから暖かいメッセージが入っていたのを思い出します。
このガイドを選んだ理由は、こちら


私が所有する、スピードスティック#1-26HOBBに付いているガイドが、このCNSGのハードリング版だったからです。
オールドな雰囲気を残しながら、リングはSicで性能アップ!
めっちゃ格好良くないですか?
現行品でもハードリング版のNガイドは売っていますが、スピードスティックに付いているものとは違うようです。
ハードリングでも性能は十分なのかも知れませんが、やっぱりリングはSicでしょう。
ちなみに、CNSGの品番に付いているCとはクロームメッキのことで、現在は環境に優しく無いので、作られなくなったようです。
現行品で、似たものを探すと、E又はPの品番が付いたものを選択するしかありません。
また、NガイドもSicリングの設定のものはなく、ライト仕様のLNか、ミディアム仕様MNの品番のものを選ぶしかありません。
最近は、(最近でも無い?)ダブルフットのガイドも、Kガイドという前側に傾斜した糸絡みの少ないガイドに変わって来ているので、そちらの選択も出来ます。
ただ、今回のように、オールドな雰囲気を残しつつ、Sicガイドで、しかも安価にとなると、デッドストックのものを探すしかないので ネットで、注意深く探すか、古くからある釣具屋さんの在庫を探すかしかないのです。
つづく
2016年03月11日
ロッドメイキング1-21
今年もこの日がきました。
私は偉そうなことは何も言えないけど、全ての被災された方にお見舞い申し上げます。
日本人が忘れてはならない日 3.11

さて、話は変わってロツドメイキングの話。
2回目の塗料の混合です。1回目と同じように主液10グラム位を目安に、紙コップに入れます。
購入した主液の量が40mlなので、2回使うともう半分無くなります。
主液の4分の1の重さの硬化剤を計って入れます。
ここで、混ぜ合わせる前に、ウレタンシンナーを入れます。
ある程度ゆるくなるように希釈して、混ぜ合わせます。気泡がかまないようにゆっくり混ぜ合わせます。
しかし、シンナーの量が少なかったのか、少し気泡がかんできました。
また、少し希釈して混ぜ合わせます。
気泡がある程度残っていますが、このまま置いて置きます。
シンナーでゆるく希釈しているので、今度はある程度の粘度が出てくるまでしばらく置いておきます。
2時間位放置して粘度を見てみると、だいぶ上がってきたように思います。
はっきり言って、気温が低すぎるので、ウレタンの粘度が高いのかもしれません。
夏場にやれば、もっとサラサラになっているのかもしれませんが、冷えて粘度が上がったのか、シンナーが揮発して粘度があがったのかがわかりません。
とりあえず、混ぜ合わせた棒の先から垂らしてみると、ソフトクリーム状に山になるようになってきました。
(この塗り頃になった粘度の見分け方の表現はどこで見たんだったけ?)
そろそろ、塗り頃のようなので、塗装してみることにします。
ブランクを塩ビパイプで延長して、ボイジャーバッテリーにガムテープで固定。
バッテリーの上下を新聞紙で養生して、ポリ容器に塗料を入れます。
この辺は試し塗りで失敗したときと同じ手順です。
あまり厚く着きすぎるのもいやですが、ツヤが出ないのもいやなので、塗装するスピードを考えます。
ティップが厚塗りになるのが一番いやなので、ティップの部分はある程度ゆっくり抜こう。
バットはデカールの部分がまだ少しでこぼこがあるので、少し厚めに塗ろう。
ということで、始め早く、ティップに向けてスピードを緩めるイメージです。
それでは、塗ってみます。せーの
おっ!行ったか?
ゴムシートの穴も元に戻っていて、液だれも無し。塗料もこぼさずに塗装できました。
仕上がりは…

書き忘れていましたが、私はロッドやルアーのハンドメイドを秘密の小部屋という自分の部屋で行っています。
これは、家を新築するときにどうしてもほしくて作った、車庫からつづくコンクリート敷きの部屋です。
この小部屋を作りたくて家を建てたと言ってもいいくらいです。(家族に怒られそうですが…)
当初は、この小部屋を使って、ルアーやロッドの塗装、スノーボードのワックス掛けなどを全て行うつもりでしたが、思った以上に部屋に荷物が入り過ぎて、思うような作業スペースが取れませんでした。
そこで、ロッドの塗装など大きいものの塗装や、スノーボードのワックス掛けを車庫の中で行うようになったのです。
車庫の中には40ワットの蛍光灯が2本の照明と、後で自分で取り付けた、20ワットの蛍光灯が1本あるのですが、明るさの点で言えば充分とは言えません。
前置きが長くなりましたが、ポリ容器をうまく抜いて塗装ができたと思っても、仕上がりまでは良く確認ができなかったのです。
バッテリーからブランクを外して、逆さにつるして乾燥させます。
1~2時間で乾燥するとのことです。
この次点ではツヤツヤの仕上がりとなったかどうかは判断できません。
乾燥を待って、明るいところで確認してみます。
つづく
私は偉そうなことは何も言えないけど、全ての被災された方にお見舞い申し上げます。
日本人が忘れてはならない日 3.11

さて、話は変わってロツドメイキングの話。
2回目の塗料の混合です。1回目と同じように主液10グラム位を目安に、紙コップに入れます。
購入した主液の量が40mlなので、2回使うともう半分無くなります。
主液の4分の1の重さの硬化剤を計って入れます。
ここで、混ぜ合わせる前に、ウレタンシンナーを入れます。
ある程度ゆるくなるように希釈して、混ぜ合わせます。気泡がかまないようにゆっくり混ぜ合わせます。
しかし、シンナーの量が少なかったのか、少し気泡がかんできました。
また、少し希釈して混ぜ合わせます。
気泡がある程度残っていますが、このまま置いて置きます。
シンナーでゆるく希釈しているので、今度はある程度の粘度が出てくるまでしばらく置いておきます。
2時間位放置して粘度を見てみると、だいぶ上がってきたように思います。
はっきり言って、気温が低すぎるので、ウレタンの粘度が高いのかもしれません。
夏場にやれば、もっとサラサラになっているのかもしれませんが、冷えて粘度が上がったのか、シンナーが揮発して粘度があがったのかがわかりません。
とりあえず、混ぜ合わせた棒の先から垂らしてみると、ソフトクリーム状に山になるようになってきました。
(この塗り頃になった粘度の見分け方の表現はどこで見たんだったけ?)
そろそろ、塗り頃のようなので、塗装してみることにします。
ブランクを塩ビパイプで延長して、ボイジャーバッテリーにガムテープで固定。
バッテリーの上下を新聞紙で養生して、ポリ容器に塗料を入れます。
この辺は試し塗りで失敗したときと同じ手順です。
あまり厚く着きすぎるのもいやですが、ツヤが出ないのもいやなので、塗装するスピードを考えます。
ティップが厚塗りになるのが一番いやなので、ティップの部分はある程度ゆっくり抜こう。
バットはデカールの部分がまだ少しでこぼこがあるので、少し厚めに塗ろう。
ということで、始め早く、ティップに向けてスピードを緩めるイメージです。
それでは、塗ってみます。せーの
おっ!行ったか?
ゴムシートの穴も元に戻っていて、液だれも無し。塗料もこぼさずに塗装できました。
仕上がりは…

書き忘れていましたが、私はロッドやルアーのハンドメイドを秘密の小部屋という自分の部屋で行っています。
これは、家を新築するときにどうしてもほしくて作った、車庫からつづくコンクリート敷きの部屋です。
この小部屋を作りたくて家を建てたと言ってもいいくらいです。(家族に怒られそうですが…)
当初は、この小部屋を使って、ルアーやロッドの塗装、スノーボードのワックス掛けなどを全て行うつもりでしたが、思った以上に部屋に荷物が入り過ぎて、思うような作業スペースが取れませんでした。
そこで、ロッドの塗装など大きいものの塗装や、スノーボードのワックス掛けを車庫の中で行うようになったのです。
車庫の中には40ワットの蛍光灯が2本の照明と、後で自分で取り付けた、20ワットの蛍光灯が1本あるのですが、明るさの点で言えば充分とは言えません。
前置きが長くなりましたが、ポリ容器をうまく抜いて塗装ができたと思っても、仕上がりまでは良く確認ができなかったのです。
バッテリーからブランクを外して、逆さにつるして乾燥させます。
1~2時間で乾燥するとのことです。
この次点ではツヤツヤの仕上がりとなったかどうかは判断できません。
乾燥を待って、明るいところで確認してみます。
つづく
2016年03月10日
ロッドメイキング1-20
最近、新しいルアーを作り始めた。
ルアー作りの中で、ブランクを削っている時が一番楽しい。
カッターで木を一心に削っている時は、他の考えごとなど忘れて夢中になれる。

さて、ロツドメイキングの話に戻ります。
ゴムシートの穴開けに成功して、ポリ容器が下までさげられたので、いよいよ塗料を入れてしごき塗装です。
シマヤの2液ウレタンを混合します。
クリアーの場合硬化剤の種類が違うので4:1の比率で混合するとのこと。
て、どうやって比率を計るのか書いてませんけど…
でも、エポキシと違い、比率はそんなにシビアでは無いようですので、体積比で混合してみることにします。
一応、電子天秤も用意して、重量比率にも対応できるように準備します。
注射器を使って主液(レジン)を計ります…
粘度がありすぎて注射器で吸い取れません。
電気ストーブで温めて柔らかくしてから吸い取ろうとしましたが、やっぱりうまく行きません。
で、よく見ると、主液のラベルに書いてある専用硬化剤と、付いてきた硬化剤の品番が違う。

しかも、4:1の比率で混合するはずが、主液40mlに硬化剤が18mlも付いてきている。
これって、硬化剤が、間違ったのが付いてきてるんじゃないの?
このまま塗装して大丈夫かい?と一抹の不安がよぎり…
シマヤさんに確認してみることにしました。
ついでに、2液の混合の仕方も聞いてみよう。商品購入したお客だから構わないでしょう。
ということで、作業を中断。メールで問い合わせをしました。
「質問1:しごき塗料主液のラベルには専用硬化剤「05-025」と印刷されているが、同梱された硬化剤には「08-251」と印刷されている。硬化剤が間違っているということはないでしょうか?
また、同主液ラベルに混合比4:1と印刷されているが、その比率で混ぜて間違いないか?(4:1であれば主液40mlに硬化剤18mlもついているのはおかしい?)
ネットショップの商品ページでは「(注) クリアー、パールホワイトクリアーのみ硬化剤の種類、混合比率が異なります。 4:1の比率で混合してください。」とあるが、画像と見比べても異なるものとは思えない。
質問2:主液と硬化剤の混合比率は体積の比率か重量の比率か?
主液の粘度が高すぎて注射器で吸い取れなかったため、重量比率(0.01g目盛りの秤使用)で混合しようと思うが問題はないでしょうか?
体積比率の場合は注射器を使う以外によい方法は無いでしょうか?」
以下、シマヤさんからの回答です。
「先日は弊社オンラインショップをご利用いただき誠にありがとうございました。
まず、質問1に関しましては、誠に申し訳ございません、こちらの手違いで主液のラベルのシールを貼り間違えてしまったようです。クリアの硬化剤は「08-251」で間違いありません。比率も4:1で混合して下さい。
混合比率に対して硬化剤の容量が多いのは、こちらも弊社都合で申し訳ございませんが、しごき塗料は弊社特注で塗料メーカーに配合してもらった塗料を、店頭で瓶に小分けして販売しておりますが、瓶のサイズが主剤用の40ml、硬化剤用の18mlの2種類しか用意が無い為、混合比4:1のクリア系塗料にもその他の混合比2:1の塗料と同じものを使用しています。ですのでクリア系塗料の場合は硬化剤が余ってしまうことになりますが何卒ご容赦下さい。
質問2に関しましては、重量比率で混合して頂ければOKです。
4:1という混合比も多少の誤差が出ても十分固まりますので、そこまで精密に量らなくてもご使用できます。」
迅速な対応ありがとうございます。
なるほど、このまま使っても大丈夫そうですね。
ということで、電子天秤により重量比率で混合することにしました。
しかし、ねばい。10グラム位を目安に紙コップに主液を入れます。
入れた主液の4分の1になるように硬化剤(ハードナー)を入れて混ぜ合わせます。
硬化剤を入れても、ねばいのは変わらず、このまま混ぜ合わせたら…
めちゃめちゃ気泡が絡んでます。
シマヤの商品説明ページには「混合後、充分に時間をおいて粘度を上げた後、しごき塗りで塗ってください。」とありますが、時間をおかなくても充分粘度が高いです。
気泡が無くなるかと時間をおいて見ましたが、いっこうに気泡は抜けません。
やばい!薄め液を一緒に買っとけば良かった。
と思ったのも後の祭り、こうなれば家にあるウレタン用のシンナーを混ぜてみます。

ウレタンクリアーのマルチトップクリアーSHを使うときは、プロタッチシンナーを使います。なので、今回もこれで薄めてみます。
余談ですが、マルチトップクリアーSHはプロタッチシンナーでもパナロックシンナーでも大丈夫ですが、パナロックの希釈にはパナロックシンナーを使うことになっています。
プロタッチシンナーでも本当はいけるんじゃないでしょうか。
混ぜ合わせたシマヤウレタンをプロタッチシンナーで薄めてみましたが、緩くはなるけれど気泡は消えません。
しばらく置いてみましたが、少し気泡が少なくなりましたが、完全には気泡は抜けませんでした。
これは、2液を混ぜ合わせる前にシンナーで希釈する必要がありますね。
今回作った塗料は塗装せずに捨てることとなりました。
つづく
ルアー作りの中で、ブランクを削っている時が一番楽しい。
カッターで木を一心に削っている時は、他の考えごとなど忘れて夢中になれる。

さて、ロツドメイキングの話に戻ります。
ゴムシートの穴開けに成功して、ポリ容器が下までさげられたので、いよいよ塗料を入れてしごき塗装です。
シマヤの2液ウレタンを混合します。
クリアーの場合硬化剤の種類が違うので4:1の比率で混合するとのこと。
て、どうやって比率を計るのか書いてませんけど…
でも、エポキシと違い、比率はそんなにシビアでは無いようですので、体積比で混合してみることにします。
一応、電子天秤も用意して、重量比率にも対応できるように準備します。
注射器を使って主液(レジン)を計ります…
粘度がありすぎて注射器で吸い取れません。
電気ストーブで温めて柔らかくしてから吸い取ろうとしましたが、やっぱりうまく行きません。
で、よく見ると、主液のラベルに書いてある専用硬化剤と、付いてきた硬化剤の品番が違う。

しかも、4:1の比率で混合するはずが、主液40mlに硬化剤が18mlも付いてきている。
これって、硬化剤が、間違ったのが付いてきてるんじゃないの?
このまま塗装して大丈夫かい?と一抹の不安がよぎり…
シマヤさんに確認してみることにしました。
ついでに、2液の混合の仕方も聞いてみよう。商品購入したお客だから構わないでしょう。
ということで、作業を中断。メールで問い合わせをしました。
「質問1:しごき塗料主液のラベルには専用硬化剤「05-025」と印刷されているが、同梱された硬化剤には「08-251」と印刷されている。硬化剤が間違っているということはないでしょうか?
また、同主液ラベルに混合比4:1と印刷されているが、その比率で混ぜて間違いないか?(4:1であれば主液40mlに硬化剤18mlもついているのはおかしい?)
ネットショップの商品ページでは「(注) クリアー、パールホワイトクリアーのみ硬化剤の種類、混合比率が異なります。 4:1の比率で混合してください。」とあるが、画像と見比べても異なるものとは思えない。
質問2:主液と硬化剤の混合比率は体積の比率か重量の比率か?
主液の粘度が高すぎて注射器で吸い取れなかったため、重量比率(0.01g目盛りの秤使用)で混合しようと思うが問題はないでしょうか?
体積比率の場合は注射器を使う以外によい方法は無いでしょうか?」
以下、シマヤさんからの回答です。
「先日は弊社オンラインショップをご利用いただき誠にありがとうございました。
まず、質問1に関しましては、誠に申し訳ございません、こちらの手違いで主液のラベルのシールを貼り間違えてしまったようです。クリアの硬化剤は「08-251」で間違いありません。比率も4:1で混合して下さい。
混合比率に対して硬化剤の容量が多いのは、こちらも弊社都合で申し訳ございませんが、しごき塗料は弊社特注で塗料メーカーに配合してもらった塗料を、店頭で瓶に小分けして販売しておりますが、瓶のサイズが主剤用の40ml、硬化剤用の18mlの2種類しか用意が無い為、混合比4:1のクリア系塗料にもその他の混合比2:1の塗料と同じものを使用しています。ですのでクリア系塗料の場合は硬化剤が余ってしまうことになりますが何卒ご容赦下さい。
質問2に関しましては、重量比率で混合して頂ければOKです。
4:1という混合比も多少の誤差が出ても十分固まりますので、そこまで精密に量らなくてもご使用できます。」
迅速な対応ありがとうございます。
なるほど、このまま使っても大丈夫そうですね。
ということで、電子天秤により重量比率で混合することにしました。
しかし、ねばい。10グラム位を目安に紙コップに主液を入れます。
入れた主液の4分の1になるように硬化剤(ハードナー)を入れて混ぜ合わせます。
硬化剤を入れても、ねばいのは変わらず、このまま混ぜ合わせたら…
めちゃめちゃ気泡が絡んでます。
シマヤの商品説明ページには「混合後、充分に時間をおいて粘度を上げた後、しごき塗りで塗ってください。」とありますが、時間をおかなくても充分粘度が高いです。
気泡が無くなるかと時間をおいて見ましたが、いっこうに気泡は抜けません。
やばい!薄め液を一緒に買っとけば良かった。
と思ったのも後の祭り、こうなれば家にあるウレタン用のシンナーを混ぜてみます。

ウレタンクリアーのマルチトップクリアーSHを使うときは、プロタッチシンナーを使います。なので、今回もこれで薄めてみます。
余談ですが、マルチトップクリアーSHはプロタッチシンナーでもパナロックシンナーでも大丈夫ですが、パナロックの希釈にはパナロックシンナーを使うことになっています。
プロタッチシンナーでも本当はいけるんじゃないでしょうか。
混ぜ合わせたシマヤウレタンをプロタッチシンナーで薄めてみましたが、緩くはなるけれど気泡は消えません。
しばらく置いてみましたが、少し気泡が少なくなりましたが、完全には気泡は抜けませんでした。
これは、2液を混ぜ合わせる前にシンナーで希釈する必要がありますね。
今回作った塗料は塗装せずに捨てることとなりました。
つづく
2016年03月09日
ロッドメイキング1-19
週末の暖かさだと、そろそろ春の釣り準備をしなきゃと思わせましたが、また冬に逆戻りで、やっぱり釣りは来月からですかね。

ABU ULTRA MAG XL-1
春の釣りで欠かせないのがこれ!
金属製の丸型リールだと、手が冷たくなるので樹脂製のリールが良いのです。
一番手前がいつも使うリール。で、左が部品取りに買ったもの。
現行のリールでは無いので、壊れたときに修理が効かないので、部品取りは必要不可欠。
現に、使い始めてすぐに、レベルワインドに不具合がでました。
そして、一番奥はワイドスプールのXL-2。
今のところ出番はありません。
2500Cとかと違い、構造が複雑なので、メンテナンスも大変なのですが、そろそろやらないいけません。
さて、ロツドメイキングの話の続き。
せっかく買った生ゴムシートも、穴の大きさの選択を誤り、またしてもシートを無駄にしてしまいました。
穴を開けて売っているシートは、機械のポンチで開けているようで、ささくれなど無く、きれいに穴が開けられています。
しかし、穴無しのシートが売られている以上、素人でも穴が開けられるということです。
1.5ミリくらいのポンチをネットで探すと、結構安く売っています。
でも、ポンチを買ってもそのサイズの穴しか開けられないので、1.5ミリの穴が開いた生ゴムシートを買うのと変わりありません。
値段も同じくらいだし…
また送料を払って、生ゴムシートを注文するのも何かしゃくに触るので、もう一度自分で穴を開けることを考えました。
ゴムシートの穴開けについて書かれているのは、富士工業のカタログだけです。
もう一度やり方で読み落としたところが無いか、読み返してみました。
「千枚通しの先をまっ赤になるまで炎で熱し、生ゴムの中心に垂直にまっすぐ刺す。※ヤケドにご注意ください」「※穴の大きさの目安は、穂先径の6割くらい。これにより、千枚通しを使うか、または求める穴の大きさに合う縫い針を使うかを決めます。」「縫い針の際は、ヤケドをしないよう革手袋、ペンチを使用してください。」「穴が開いたら…」
と、書かれている説明はこれだけです。
ブランクの穂先の太さは約2ミリです。使う道具は縫い針ではなく、千枚通し。これは間違いありません。
となると、間違っているのは、「千枚通しの先を真っ赤になるまで炎で熱し…」の部分か?
今までは、ライターであぶってススが着いたので、真っ赤になっているかどうかわからないまま、ゴムシートに刺していました。
ここか?問題は?
と言うことで、ライターで今まで以上にあぶって、真っ赤にしてみようと思いました。
火事は起こしたくないので慎重に…
で、10秒くらい熱していると、ススで黒くなった千枚通しの先が、赤くなってきているように見えました。
お、赤くなってきてる! 今だ!と、ゴムシートに千枚通しを刺すと、明らかに今までとは違う感じ。
とろっとゴムが溶けて、千枚通しの太さに穴が開きました。
熱しかたが甘かった時は、千枚通しの先の部分で穴が開いた後は、ゴムの弾力で穴が広がり、穴のまわりは焦げてささくれるだけで、刺した針の太さにはなりませんでした。
今回は、刺した針の太さまでゴムが溶け、穴のまわりもきれいに溶けています。

これかー!熱しかたが足りなかったのかー!
ようやく、ゴムシートに穴を開けるというひとつの作業のやり方がわかりました。
これで、今後は、好きな大きさに穴を開けることができるでしょう。
新しく穴を開けたゴムシートを、ポリ容器にセットして、水をつけて下までさげてみました。
今回はゴムが裂けずに、下までさげることができました。
水を入れて仮想しごき塗装をやってみます。
うまくティップまで抜くことができました。ゴムシートの穴もティップより細く戻っていて、液だれは起きそうにありません。
やっぱり専門の道具は違うな。ゴムの弾力も、ホームセンターのものよりはかなり良さそうです。
今思うと、ホームセンターのゴムシートで、穴を開けるのに成功していたら、弾力の無いホムセンゴムシートで、何度も塗装を失敗して、未だに正解が見えていなかったかもしれません。
とりあえず、ゴムの穴開け問題が解決したので、しごき塗装の再開です。
つづく

ABU ULTRA MAG XL-1
春の釣りで欠かせないのがこれ!
金属製の丸型リールだと、手が冷たくなるので樹脂製のリールが良いのです。
一番手前がいつも使うリール。で、左が部品取りに買ったもの。
現行のリールでは無いので、壊れたときに修理が効かないので、部品取りは必要不可欠。
現に、使い始めてすぐに、レベルワインドに不具合がでました。
そして、一番奥はワイドスプールのXL-2。
今のところ出番はありません。
2500Cとかと違い、構造が複雑なので、メンテナンスも大変なのですが、そろそろやらないいけません。
さて、ロツドメイキングの話の続き。
せっかく買った生ゴムシートも、穴の大きさの選択を誤り、またしてもシートを無駄にしてしまいました。
穴を開けて売っているシートは、機械のポンチで開けているようで、ささくれなど無く、きれいに穴が開けられています。
しかし、穴無しのシートが売られている以上、素人でも穴が開けられるということです。
1.5ミリくらいのポンチをネットで探すと、結構安く売っています。
でも、ポンチを買ってもそのサイズの穴しか開けられないので、1.5ミリの穴が開いた生ゴムシートを買うのと変わりありません。
値段も同じくらいだし…
また送料を払って、生ゴムシートを注文するのも何かしゃくに触るので、もう一度自分で穴を開けることを考えました。
ゴムシートの穴開けについて書かれているのは、富士工業のカタログだけです。
もう一度やり方で読み落としたところが無いか、読み返してみました。
「千枚通しの先をまっ赤になるまで炎で熱し、生ゴムの中心に垂直にまっすぐ刺す。※ヤケドにご注意ください」「※穴の大きさの目安は、穂先径の6割くらい。これにより、千枚通しを使うか、または求める穴の大きさに合う縫い針を使うかを決めます。」「縫い針の際は、ヤケドをしないよう革手袋、ペンチを使用してください。」「穴が開いたら…」
と、書かれている説明はこれだけです。
ブランクの穂先の太さは約2ミリです。使う道具は縫い針ではなく、千枚通し。これは間違いありません。
となると、間違っているのは、「千枚通しの先を真っ赤になるまで炎で熱し…」の部分か?
今までは、ライターであぶってススが着いたので、真っ赤になっているかどうかわからないまま、ゴムシートに刺していました。
ここか?問題は?
と言うことで、ライターで今まで以上にあぶって、真っ赤にしてみようと思いました。
火事は起こしたくないので慎重に…
で、10秒くらい熱していると、ススで黒くなった千枚通しの先が、赤くなってきているように見えました。
お、赤くなってきてる! 今だ!と、ゴムシートに千枚通しを刺すと、明らかに今までとは違う感じ。
とろっとゴムが溶けて、千枚通しの太さに穴が開きました。
熱しかたが甘かった時は、千枚通しの先の部分で穴が開いた後は、ゴムの弾力で穴が広がり、穴のまわりは焦げてささくれるだけで、刺した針の太さにはなりませんでした。
今回は、刺した針の太さまでゴムが溶け、穴のまわりもきれいに溶けています。

これかー!熱しかたが足りなかったのかー!
ようやく、ゴムシートに穴を開けるというひとつの作業のやり方がわかりました。
これで、今後は、好きな大きさに穴を開けることができるでしょう。
新しく穴を開けたゴムシートを、ポリ容器にセットして、水をつけて下までさげてみました。
今回はゴムが裂けずに、下までさげることができました。
水を入れて仮想しごき塗装をやってみます。
うまくティップまで抜くことができました。ゴムシートの穴もティップより細く戻っていて、液だれは起きそうにありません。
やっぱり専門の道具は違うな。ゴムの弾力も、ホームセンターのものよりはかなり良さそうです。
今思うと、ホームセンターのゴムシートで、穴を開けるのに成功していたら、弾力の無いホムセンゴムシートで、何度も塗装を失敗して、未だに正解が見えていなかったかもしれません。
とりあえず、ゴムの穴開け問題が解決したので、しごき塗装の再開です。
つづく